この子にどこまで手を貸すべき?
手を差し伸べすぎると、子どもの主体性が育たないのでは…
でも、困っているのに助けを求められない子もいるのでは…
と迷ったことはありませんか?
教育現場でも家庭でも、この支援のバランスに悩む人は多い。
この記事では、どのタイミングで見守り、いつ手を貸すべきなのか最適なバランスの見つけ方を紹介していくよ!
「見守る」と「支援する」の両極に価値がある
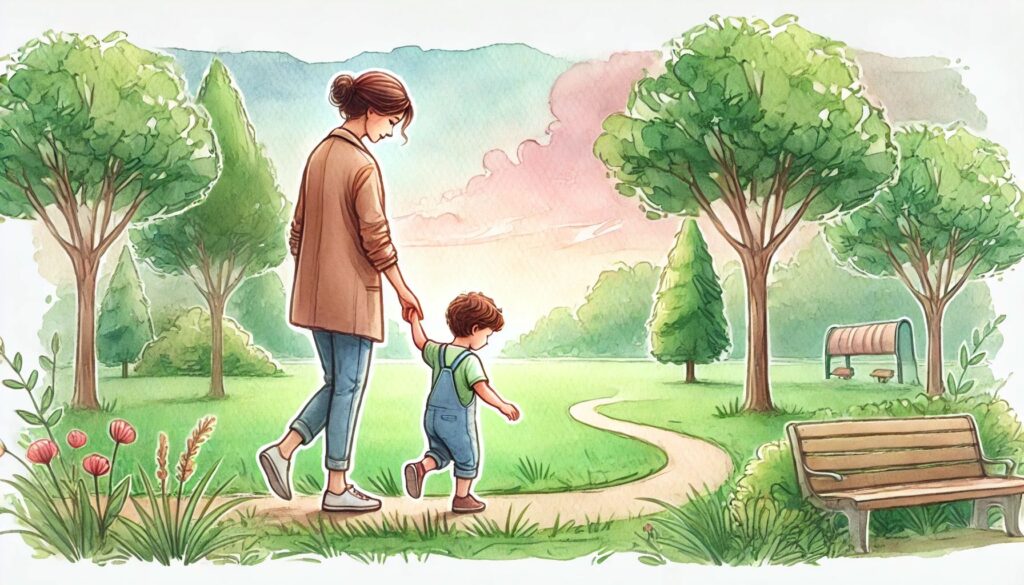
子どもへの関わり方には、大きく分けて「見守る」と「支援する」の二つのアプローチがある。それぞれに意味があり、どちらが正解というものではないんだよね。大事なのは、子どもの成長に合わせてバランスを取ること。
「見守るだけ」では不十分なケースもある
「子どもを信じて見守ることが大切」と言われるけど、それだけでは不十分な場合もある。
例えば、
- 読み書きに困難を抱えているのに、適切なサポートがない。
- 人間関係でトラブルを抱えているのに、大人が気づかず孤立してしまう。
- 助けを求めることが苦手で、ずっと困ったままになってしまう。
こんなとき、適切な支援をすることで、子どもは「できる経験」を積み、自信をつけていくんだ。
手を貸しすぎると、自立を妨げることもある
一方で、なんでも先回りして手を貸しすぎると、子どもが自分で考える機会を奪ってしまう。
- 失敗する経験が少なくなり、挑戦する意欲が下がる。
- 「大人がいないとできない」と思い込み、依存心が育つ。
- 自分で問題解決する力が身につかない。
特に、発達に特性がある子どもへの支援では、困る前に助けることが習慣になりやすい。でも、それが子どもの成長を妨げることもあるんだ。
大切なのは「行ったり来たり」すること
じゃあ、「見守る」と「支援する」、どっちが正解なの?
答えは、「どちらも大切で、状況に応じて行き来すること」!
- 子どもが自分で考えられそうな場面では、あえて見守る。
- 本当に困っているときは、適切なサポートをする。
- 「あと一歩が踏み出せない」ときは、背中を押してあげる。
このように、見守りと支援を行き来しながら、その子に合った関わり方を見つけていくことが大切なんだ。
見守ることも、必要な支援をすることも、「子どもを信じる」ことの一部
「見守る」と「支援する」は対立するものではなく、どちらも「子どもを信じる」姿勢の現れです。
- 見守ること → 子どもが自分の力で成長することを信じる。
- 支援すること → 必要な場面で適切なサポートを提供し、成長を促す。
つまり、私たち大人の役割は、子どもを「できない存在」として見るのではなく、「成長する力を持った存在」として関わることなのです。
どこまで手を貸す?最適なバランスの見極め方
子どもが成長するには、大人がどこまで手を貸すべきか見極めがが重要。過剰な支援は自立を妨げるし、放置しすぎると成長の機会を逃してしまう。だから、ここでは3つの視点を意識してバランスを取るようにしてみて!
① 子どものサインを見極める
- 自分で考えようとしているか? → もう少し見守る。
- 明らかに困っているか? → 最小限の手助けをする。
- できそうなのに「できない」と言っている場合は? → 少し背中を押す。
② 「手を貸しすぎたかな?」と感じたら
- すぐに答えを教えず、「どうしたらいいと思う?」と問いかける。
- 「やってあげる」のではなく、「一緒に考える」関わり方をする。
③ 「見守りすぎたかな?」と感じたら
- 子どもが何度も失敗して自信をなくしていないか?
- 「助けを求める力」が育っていないなら、声をかけるタイミングを考える。
「見守り」と「支援」のバランスを取る具体例
日々の関わりの中で、どうやってこのバランスを調整すればいいのか、具体的な方法を紹介するね。
学校・家庭で実践できる声かけ例
日常のさまざまな場面で、見守りと支援の使い分けが求められるよ。こんな声かけを意識すると、子どもが自分で考える力を伸ばしながら、必要なサポートを受けられる。
- 失敗したとき:「どうしたらうまくいくかな?」
➡まずは子どもに考えさせ、解決策を自分で見つける機会を与える。 - 困っているとき:「手伝ってほしい?」
➡自分でやるのが難しい場合、必要な範囲で手を差し伸べる。 - 頑張っているとき:「ここまでできたね!」
➡達成した部分を認めつつ、次のステップへの意欲を引き出す。
放課後等デイサービスの実践例
支援施設や学校では、子ども一人ひとりの特性に合わせて見守りと支援のバランスをとることが求められるよ。特に放課後等デイサービスでは、こんな工夫が効果的↓。
- 子どもに合わせて支援の強弱を調整する仕組みを作る。
例えば、できるだけ子ども自身に選択肢を与え、主体的に行動できる環境を整える。
- コーチング研修を取り入れ、支援の質を高める。
スタッフが適切にコーチングとティーチングを使い分けられるよう、研修をする。
まとめ
最適な支援のバランスを見つけることは、子どもの成長を支える上でとても大事。
- 「見守る」と「支援する」のどちらにも価値がある。
- 子どもにとってのベストバランスを探ることが大切。
- 手を貸す前に、一度子どもの様子を観察してみる。
子どもが自分の力を発揮し、成長していくためには、大人の関わり方が大きく影響する。時には見守り、時には手を差し伸べることで、子どもは安心して挑戦し続けられる。
今後も、教育や福祉の現場で「最適な支援のバランス」を模索しながら、子どもたちの未来を支えていこう!
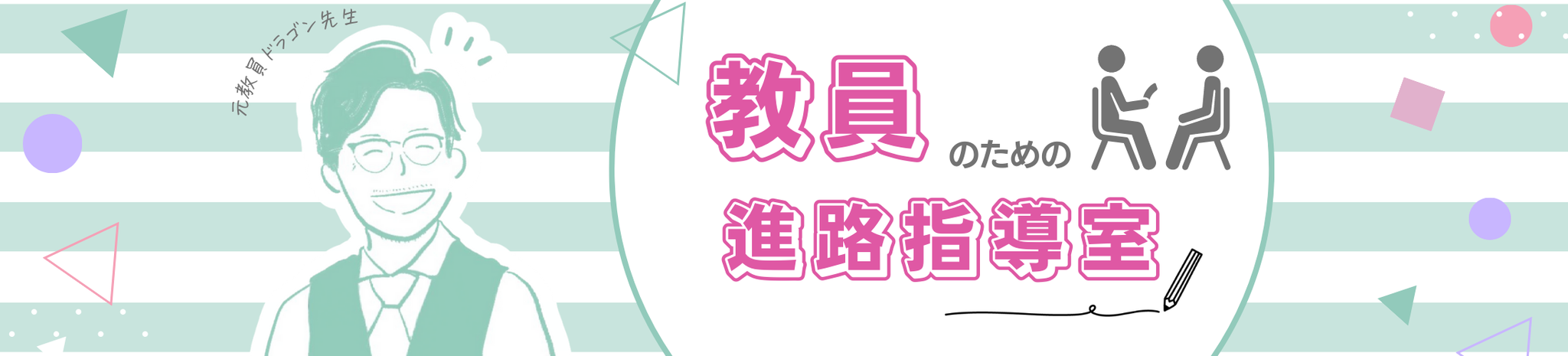

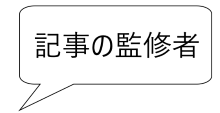
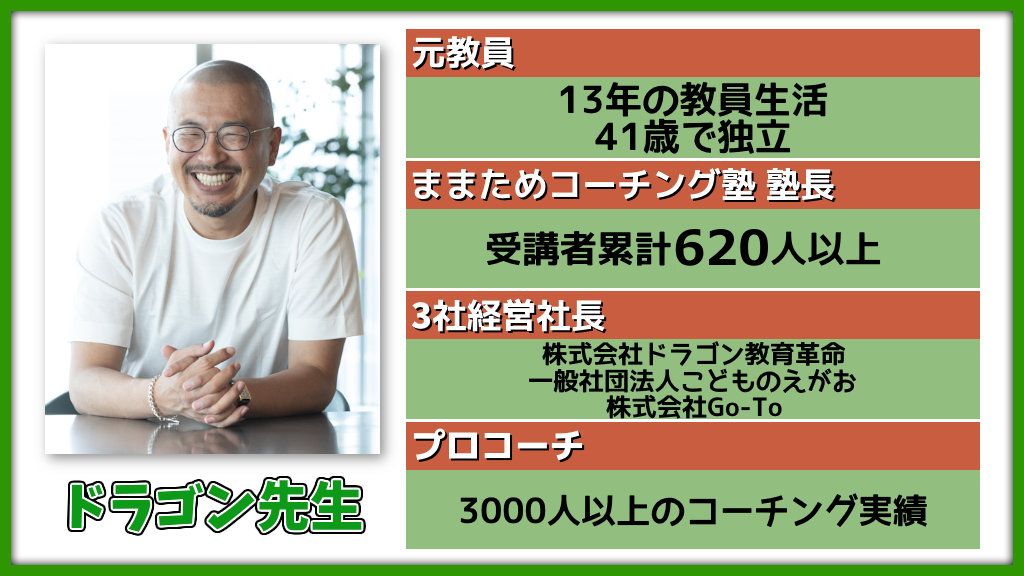
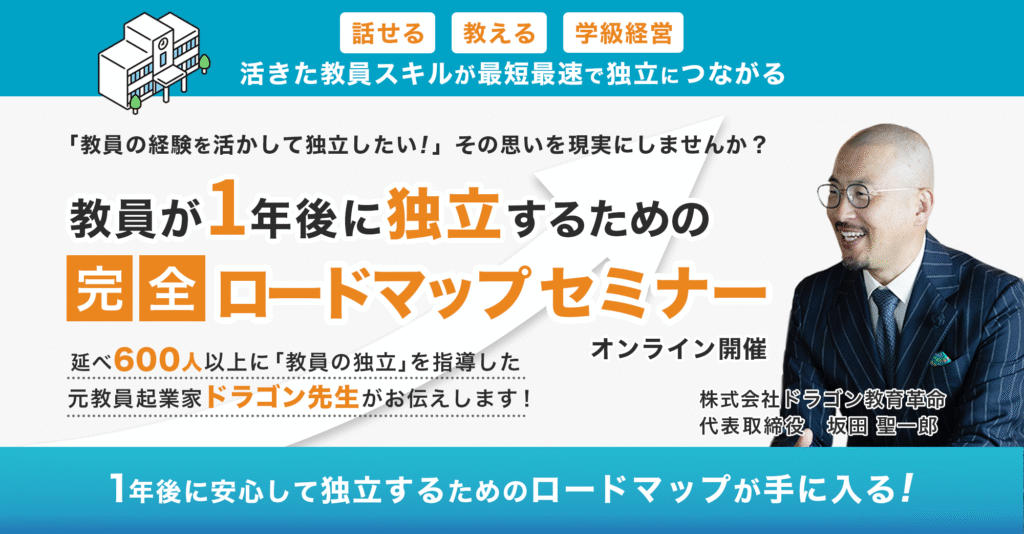

コメント